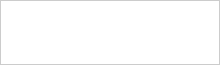「日本創倫株式会社様の許諾を得てsampleとして使用させていただいています。」
(見本)保険コンプライアンスオフィサー編
Q1:保険コンプライアンスオフィサーとは、どんなことをする人ですか?
当社の保険コンプライアンスオフィサーは、日本コンプライアンス・オフィサー協会が主催する資格を取得し、保険募集業務に精通している人です。
具体的には、保険会社や保険代理店など保険事業者に対し、保険募集業務および顧客保護の管理態勢、コンプライアンス態勢の適切性、ならびに適正な業務継続性について、公正かつ独立の立場で、総合的な視点から分析・検証・評価・提案・指導を行います。
Q2:保険コンプライアンスオフィサーと内部監査人は、どう違うのですか?
内部監査人は、自社組織の経営目標が効果的に達成できるように、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、意見を述べ、助言・勧告を行う組織内部の社員による監査人のことですが、保険コンプライアンス・オフィサーは、検査する企業が保険業法や社内ルールなどに従い、適正かつ法令遵守された経営態勢や組織の内部管理態勢となっているか法的根拠による検査・指導教育する保険専門の外部コンサルタントで、経営や人材教育作りを支援する人のことです。
Q3:保険コンプライアンスオフィサーになるには、どうすればなれますか?
当社では、日本コンプライアンス・オフィサー協会が主催する「保険コンプライアンス・オフィサー」2級資格を取得、または、当社のオフィサー養成講座を受講・認定を受け、当社のマニュアルおよび手順書等が研修・説明会で理解できればなれます。
Q4:保険コンプライアンスオフィサーが対象とする保険会社や代理店などは、どのくらいありますか?
保険業界(損害保険会社・生命保険会社・代理店)の規模(2016年度末)は、保険会社(国内損保社28社、外国損保会社12社、生命保険会社41社、少額短期保険業者91社)および代理店(約19万6千店)となっています。
Q5:保険コンプライアンスオフィサーに依頼するメリットは何ですか?
自社の点検や保険会社の監査等は形式的になりやすく、法的根拠に基づく点検・課題の発見、指導が不十分な場合が多くなりがちです。一方、保険コンプライアンス・オフィサーは、企業リスクに関する保険専門の独立した企業リスクコンサルタントとして、法的視点による検査・指導教育を行い適正な業務運営や自己管理および経営安定化が図れるようになります。
Q6:監査による代理店評価は、どのように行うのですか?
金融庁の保険検査方針の基本的な考え方を踏まえ、代理店評価項目(6項目: ①経営管理(ガバナンス)態勢、 ②法令等遵守(コンプライアンス)態勢、 ③保険募集管理態勢、 ④顧客保護等管理態勢、 ⑤募集人教育指導管理態勢、 ⑥ITオペレーショナル・リスク等管理態勢 )について、外部の視点で適正な監査を実施します。
また、評価方法は、各評価項目について4段階(評価ランク:A、B、C、D)評価を行い、問題点の指摘や重要なリスクの分析および本質的な改善提案により内部管理体制の構築を支援します。
Q7:監査実施後の代理店評価の結果は、どのように証明されるのですか?
各評価項目について監査およびフォロー監査実施後、当社の評価基準により、総合的に4段階(A・B・C・D)評価され、「代理店評価ランク認定証」を発行します。
また、毎年監査を継続実施する代理店についても監査終了後、「〇年・代理店評価ランク認定証」を発行します。
Q8:具体的な監査は、どのような内容で何日くらいかかりますか?
企業の規模や要望により監査内容が異なりますが、標準的な小規模代理店(10名以下)の監査(例)は、以下の通りで、延べ日数で約2日間です。
【小規模代理店の標準的な監査(例)】
(1)ファーストステージ:現状把握のための監査とその問題点・課題の監査報告および改善提案を行います。
①基本契約締結、監査内容・スケジュールや費用など契約内容の事前打合せ、監査の社内通知(0.5日=0.5日×1名:監査費用のご請求)
↓
②経営者・管理部署責任者の監査(ヒアリング)・点検モニタリングの実施(0.5日=0.5日×1名:経営管理・社内規則ルールの確認・把握)
↓
③営業部門の監査および点検モニタリングの実施 (0.5日=0.5日×1名:含む、募集人ヒアリング)
↓
④監査結果の報告・評価(0.5日=0.5日×1名:監査結果および課題報告と改善提案・アドバイス)
(2)セカンドステージ:監査指摘事項の改善状況を確認・報告・評価、および改善提案を行います。
以下、(1)ファーストステージと同様、PDCAサイクルにより確認監査を実施します。
(3)サードステージ:継続監査により、社内の態勢整備状況を確認し、社内規則ルールの定着状況や適正な募集管理態勢の履行状況を確認・評価します。
以下、(1)ファーストステージと同様、重要事項や過去の指摘事項を重点にPDCAサイクルにより継続監査を実施します。
(見本)登録鑑定人編
Q1:鑑定人とは、どんな人ですか?
鑑定人は、保険会社から委託を受けて、保険の対象である財物(建物・家財等)の保険価額(時価額)の評価、火災や地震が発生した場合の損害額の算定、事故状況・原因の調査ならびにそれらに関連する一連の業務を行います。
また、![]() 一般社団法人日本損害保険協会が実施する損害保険登録鑑定人試験に合格し、登録された方を損害保険登録鑑定人(以下「登録鑑定人」という)といいます。
一般社団法人日本損害保険協会が実施する損害保険登録鑑定人試験に合格し、登録された方を損害保険登録鑑定人(以下「登録鑑定人」という)といいます。
Q2:鑑定人(正式名称(「損害保険登録鑑定人」)になるためには、どうすればいいですか?
保険会社が鑑定業務を委託する際、鑑定人資格者を前提としていることから、鑑定人試験に合格し、損保協会に登録したうえで、鑑定事務所などに所属し鑑定業務を行います。
なお、一般社団法人日本損害保険協会が実施する3級認定試験は、年2回(1月・7月)実施されています。
Q3:最初に受験する3級鑑定人試験、何か受験資格や条件等が ありますか?
3級鑑定人試験は、年齢、学歴、国籍等に関係なく、以下に該当する者を除きどなたでも受験することができます。
- 暴力団員(暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当する
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
- 反社会的勢力を不当に利用している
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している
- 自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、威力または詐欺的言動その他違法ないし不当な言動を行っている
Q4:鑑定人試験にはどのような種類がありますか?
鑑定人試験は、鑑定業務に必要な知識を3段階(1・2・3級)にランク付けしたランクアップ技能試験ですので、3級鑑定人試験を受験せず、直接2級または1級鑑定人試験を受験することはできません。
Q5:3級鑑定人試験にはどのような試験科目がありますか?
3級鑑定人試験の試験科目および単位は、下記の通りです。
| 3級鑑定人試験科目 | (1)保険・一般常識 |
| (2)電気・機械 | |
| (3)建築 |
Q6:3級鑑定人試験には試験科目の免除制度がありますか?
あります。鑑定業務に有用な一定の公的資格(一級・二級建築士)を有する方については、3級の「建築」試験科目が免除されます。
試験免除を希望される方は、受験申請書類とともに受験免除を証明する書類(免許証・免除等)のコピーを損保協会宛に提出してください。
Q7:鑑定人試験の中で、特に3級鑑定人試験は、3科目(「建築免除」の方は2科目)で全科目60点以上でないと合格できませんが、何か効率的な勉強方法がありますか?
勉強方法は、人によって異なるので一概にはいえませんが、過去問題を勉強し各試験科目の出題傾向の特色等を理解してから、過去に出題された箇所を中心にテキストを精読する方法が良いと思います。
Q8:日本損害保険協会では鑑定人試験のための講習会やセミナー等は行っていますか?
損保協会では行っておりません。しかし、当社では、どの地域でも、どの時間帯でも研修が受けられるように![]() eラーニングを活用した
eラーニングを活用した![]() 3級鑑定人用eラーニング研修を実施しています。
3級鑑定人用eラーニング研修を実施しています。
Q9:鑑定人試験(3級)は、どの程度の合格率ですか?
各試験科目の難易度等によって変わり、一概に何%とは言えませんが、3級は、20~30%を合格率の目安と言われてます。特に3級試験は、全科目60点以上でないと合格できませんので、全科目の理解が必要です。
Q10:鑑定人の登録申請手続き・手数料等について教えてください。
「損害保険登録鑑定人」認定試験に合格後、同協会に鑑定人として登録申請する場合は、下記の手続きが必要となります。
- 登録料2,160円(税込み)の振込み。
- 所定の登録申請書に必要事項を記入し、提出。
なお、詳細については、同協会の登録申請手続きをご確認ください
Q11:その他、上記以外についてはどこを見ればよいですか?
![]() 一般社団法人日本損害保険協会の
一般社団法人日本損害保険協会の![]() 鑑定人Q&A(
鑑定人Q&A( ![]() 「損害保険登録鑑定人」認定試験、
「損害保険登録鑑定人」認定試験、![]() 受験および登録申請書類、
受験および登録申請書類、![]() 3級損害保険登録鑑定人認定試験、
3級損害保険登録鑑定人認定試験、![]() テキスト・過去問題等)を参照ください。
テキスト・過去問題等)を参照ください。
(見本)教育研修編
Q1:eラーニングとは?
eラーニングとは、パソコンやコンピュータネットワークなどを利用して、企業における能力開発・知識習得を効率的、効果的に行うための学習形態です。集合研修で行う場合と比べ、時間や場所を限定されずに学習機会を得ることができるのが特徴です。
Q2:学習者から見たeラーニングの学習方法によるメリット・デメリットを教えてください。
メリット・デメリット一覧です
| 学習方法 | メリット | デメリット |
| eラーニング |
|
|
Q3:ユーザID・パスワードを忘れてしまったのですが?
受講開始日より前にお送りしております 「開講のご案内」 メールに記載されておりますので、ご確認ください。なお、メールが見つからない場合は、![]() お問い合せフォーム内の 「お問合せ内容」 に受講コース名称、ご登録メールアドレスをご記入の上、ご連絡ください。
お問い合せフォーム内の 「お問合せ内容」 に受講コース名称、ご登録メールアドレスをご記入の上、ご連絡ください。
Q4:ユーザ登録をしたのですが、登録メールが届きません。
フリーメールアドレスをご利用の場合
迷惑メールとして認識されている可能性があります。
フリーメールアドレスをご利用の場合、弊社からのメールが不達となったり、受信に時間がかかるケースが確認されております。
Q5:ログインIDが分かりません。
ユーザ登録にてご登録いただきました、メールアドレスがログインIDとなります。ログインID(メールアドレス)は大文字、小文字が区別されるのでご注意ください。
Q6:パスワードが分かりません。
![]() パスワード・リマインダーをご利用いただき、ご確認ください。
パスワード・リマインダーをご利用いただき、ご確認ください。
Q7:既に、eラーニングシステムを社内に導入済みです。この場合、教材(コンテンツ)のみを購入することはできますか?
可能です。教材(コンテンツ)のみ提供の場合、作成費の見積りをご提示します。なお、教材(コンテンツ)は、PowerPoint等のデジタルデータでご提供いたしますが、 PowerPointの枚数・撮影時間・動画の長さ・ファイルサイズ等で費用は変動いたします。 詳しくはお問い合わせください。